発達障害の子どもに家庭でのルールを設定するコツ
- Colorful Kids
- 2024年9月13日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年9月20日
発達障害のある子どもは、様々な特性からルールを守ることが難しいことも多いですよね。
しかし、生活をしていく中で全くルールを設けないとメリハリを持って過ごすことができなくなってしまいます。
そこで、発達障害のある子どもに家庭でのルールを設定するコツについてご紹介します。
ぜひ参考にして、スムーズに生活や遊びができるよう工夫してみてください。
もくじ
1. 簡潔にわかりやすいルールにする
発達障害のある子どもは、いくつものルールを順序だてて頭の中で整理することが苦手な場合が多いです。
一度に複数のルールを設定するのではなく、できるだけ一つの指示を簡潔に伝えてわかりやすくしましょう。
「一つできたら次の指示を出す」というやり方が合う子もいれば、チェックリストを作って「見通しを持ちながら一つずつクリアしていく」という方が合う子も。
子どもの性格や特性を見極めたり、様々な方法を試したりしながらルールを設定してみてください。
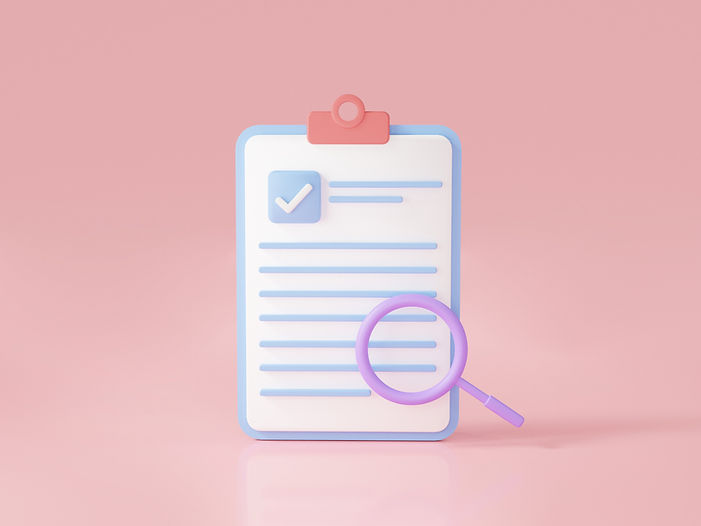
2. 事前に決めたり伝えたりする
発達障害の特性で“感情が優位になってしまう”という特徴があります。
例えば、遊びに夢中になっている途中で急に「もう終わり」と伝えても「嫌だ!」「まだ遊びたい!」という感情になるので指示が入りにくいです。
また、勝ち負けのある遊びでは「負けたくない」という感情からルールを破ってしまったり、負けると怒って手がつけられなくなったりすることも。
それらを回避するためにも、ルールは必ず事前に伝えましょう。
冷静な時にしっかりルールを確認しておくことで、遊びの途中でも思い出しやすくなったり感情的になりすぎることを抑えたりする効果も期待できます。

3. 見える化する
発達障害のある子どもは目から入る情報に意識が向きやすいため、ルールを見える化しておくのも効果的です。
例えば、生活や身支度の流れを表にして壁に貼っておいたり、遊びのルールを箇条書きにしたりするとわかりやすいでしょう。
クリアしたらチェックまたはマグネットの印をつける、ルールを守れたらシールを貼る、など子どもが流動的に関われるものにすると続けやすいです。
遊びの時間や生活の区切りにルールを設ける場合は、時計に目印をつけておくと言葉だけで「〇時だから終わりだよ」と伝えるよりも、視覚的な効果があります。

まとめ
家庭でのルールを設定する際には、発達障害のある子どもの特性を考慮しながら工夫していくことが大切です。
曖昧な表現や複雑なルールは苦手な傾向があるので、「簡潔に・事前に・見える化」という3点をポイントにするとスムーズになります。
ルール作りのコツを掴んで、親も子どもも笑顔で楽しく過ごせる時間が増えるといいですね。



コメント